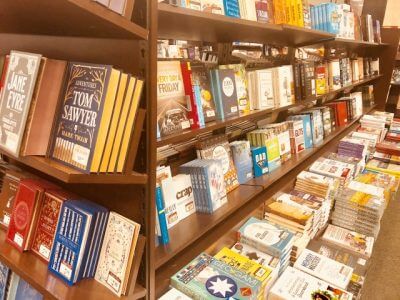2022年(令和4年)の12月頃だったと思います。
新聞朝刊の2面〜3面辺りの紙面下部には、
大手出版社の新刊広告
が載っているのが常です。
ある日、その欄に「集英社」の広告が大きく出ていました。
その中の
「集英社新書」
の、ある新刊名に目が留まりました。
「ファスト教養 10分で答えが欲しい人たち」・・・。
「『ファスト教養』?どういう意味?」
著者名を見ると
「レジー」・・・。
「誰?聞いたことない人だが・・・。ブロガーかYoutuberか?」
非常に気になりましたが、その時はそれで終わりました。
Amazonで『おすすめの本』に。縁を感じて購入!
しばらくして、別の本を買うためにAmazonのサイトを閲覧していました。
その際、
「あなたにおすすめの本」
の中の一冊に、「ファスト教養」が現れました。
これも何かの縁だと思い、他の本と一緒に購入しました。
著者紹介を読むと、「レジー」氏は1981年生まれのライター・ブロガー。
音楽関連の文章を、各種媒体に発表なさっているとのこと。
しかし本業は会社員で、事業戦略やマーケティング戦略に従事なさっているそうです。
著者名の下に
「regista13」
と書かれており、Twitterのアドレスにも使われています。
「regista(レジスタ)」は、イタリア語で
「監督、演出家」
を指す言葉ですが、サッカー用語ではいわゆる
「ボランチ」(守備的ミッドフィールダー)
を意味します。
サッカーファンなのかもしれません。
『教養』を手軽かつ効率的に得ようとする社会状況を解説!
「音楽ライターで、マーケティングに従事してる人が『教養』?一体何の話を書いてるんだ?」
そんな疑問をお持ちの方も多いでしょう。
しかし、本書の「はじめに」の7ページ分に、本書で伝えたいことのエッセンスが濃縮されています。
「ファスト教養」
とは著者の造語で、ファストフードから由来しています。
「なるべく手っ取り早く、かつ効率的に教養を身につけたい。」
という考え方や、そうした需要に合わせたコンテンツ一般を指しています。
本来「教養」とは、本書でも言及されているように、
明確な基準や範囲
がありません。
そして、長い時間をかけて少しずつ
「教養のある人」
になっていくイメージがあります。
そうした曖昧なはずの教養を、速く効率的に身につけて、何をしようというのでしょうか?
また、そうした世の中の流れは、どのように醸成されてきたのでしょうか?
そういう現象を、本書は詳細に解説していきます。
『教養』は金儲けのためのツール?
「第一章 ファスト教養とは?ー「人生」ではなく「財布」を豊かにする」
では、教養が
「ビジネスの役に立つツール」
すなわち
「金儲けに直結する知識」
として認識される現状を、実例を挙げて説明しています。
たとえば古典文学や1990年代J-POPなど、目上の人や仕事の取引相手に話を合わせられる知識が
「ビジネスパーソンの教養」
と位置付けられます。
それを武器の一つとして上手く世渡りし、お金に結び付けるため、教養を身につけようというわけです。
しかも、内容を深く学んで詳しい知識を蓄えるより、大雑把でざっくりした
「相手の話に合わせられるレベル」
が到達点となっています。
できれば
「あまり時間をかけず、要領よく」
身につけたい・・・。
そういう人が増えているそうです。
本来の教養からは、遠く離れてしまっていますが・・・。
『社会的転落』への不安がファスト教養への需要に!
「第二章 不安な時代のファスト教養」では、なぜ多くの働く人々が「ファスト教養」を欲しがるのかが語られます。
そうした人々に共通する発想が
「教養がない」→「仕事で結果を出せない」→「評価が下がる」
→「使えない人材と判断される」→「地位・仕事を失う」
→「競争から脱落し、下層へ転落する」
です。
傍から見ればまるでマンガのような、飛躍し過ぎの発想です。
しかしビジネス社会の最前線で奮闘する人たち、特に
周囲が羨むほどのキャリアを歩んでいる人たち
ほど、こうした強迫観念に囚われがちになるそうです。
そうした人々の不安が、一定の需要を生み出します。
その代表例が、
池上彰氏の著作
中田敦彦氏(オリエンタルラジオ)のYouTubeチャンネル
です。
本章では、中田氏に限らずYouTubeで人気を博す
「インフルエンサー」
の功罪についても語っています。
『自己責任論』がファスト教養隆盛の下地に!
「第三章 自己責任論の台頭が教養を変えた」では、まず最初に「ファスト教養」の主要な伝道師とも言うべきインフルエンサーたちの
「弱者に対する視線の冷たさ」
を指摘しています。
メンタリストDaiGo氏の生活保護受給者・ホームレスに対する差別発言は、ネット上で大炎上しました。
しかし本書では、程度や表現の差こそあれ、「ファスト教養」派のインフルエンサーたちには、DaiGo氏と同様の考え方が内在していると説明しています。
「成功者(経済的)= 偉い」
「敗者(貧困)= 努力不足」
「敗者、弱者= 自己責任」
といった概念が、「ファスト教養」の底に流れているというものです。
著者はその発端を、2000年代前半(小泉政権下)の
「自己責任論」
と捉えています。
そうした時期に出現した
ホリエモンこと堀江貴文氏
橋下徹氏
勝間和代氏
ひろゆきこと西村博之氏
等・・・。
これらの人々に共通するのは、やはり
「自己責任」
「個人主義」
そして
「公(おおやけ)への関心の薄さ」
です。
その後の第二次安倍政権期においても、彼らの多くは同じようなメッセージを発信し続けています。
それと密接に関連するのが「ファスト教養」だという著者の指摘は、非常に鋭いと思います。
『生き残りたい』ビジネスパーソンの本音!
「第四章 『成長』を信仰するビジネスパーソン」では、著者がビジネス書のオンライン読書会で知り合った、二人の参加者へのインタビューが掲載されています。
二人ともキャリア的には、いわゆる
「成功している人」
だそうです。
しかしインタビューでは、二人とも
「成長」
「スキルアップ」
「お金」
「焦り」
といった、本書で頻出するキーワードを連発しています。
勝ち組の人たちも、
「脱落への恐怖」
からは逃れられないことが窺えます。
映画、ヒットチャート・・・あらゆる文化が『ファスト教養のコンテンツ』に!
「第五章 文化を侵食するファスト教養」では、様々な文化が
「ファスト教養のコンテンツ」
に取り込まれて変質していく様が描かれています。
最近流行りの
「映画を早送りで観る」
「本の題名にやたら『教養としての○○』が付く」
にも言及されています。
また、AKB48に代表されるアイドルグループによる
「チャートハック」
により、ヒットチャートの信憑性が消失したことも指摘されています。
さらに、そうしたグループ内での過酷な競争が
「生き残りのための成長・スキルアップ」
という、「ファスト教養」にピッタリの環境を自ら生み出してしまったことにも触れています。
同じく過酷な競争を勝ち抜いた、サッカーなどの有名スポーツ選手による
「自己啓発的メッセージ」(書籍やSNSなどで)
も、「ファスト教養」を普及させる燃料となっているとの著者の視点は、大変興味深いものです。
ファスト教養『全否定』ではなく、上手に関わるべき!
「第六章 ファスト教養を解毒する」では、現在の日本社会で単に「ファスト教養」を全否定しても、無意味であると主張しています。
「ファスト教養」を決して丸呑みせず、かと言って全く無視もせず、その毒にやられないように上手に関わっていくべきとの意見です。
至極真っ当な意見です。
撲滅できない以上は、自分で「解毒」できるように心掛けるのが最善策でしょう。
最後に・・・。
本書の最後には「おわりに」という章があります。
ここにも、著者の言いたいことのエッセンスが濃縮されて詰まっています。
ただ、本書を最初から読んで来ないと、この章の内容の素晴らしさは実感できないでしょう。
本書は、単に特定の人物を糾弾するという内容ではありません。
鋭い批判を加えた人物についても、評価すべき点は公平に評価するというスタンスを貫いています。
著者自身も、若手社会人の頃には「ファスト教養」的な考え方に傾いたり、「チャートハック」に加担するような行動をしたと、正直に語っています。
そのため、本書には「上から目線」的な感じが全くありません。
鋭い社会批判でありながら、読後感は良い意味ですっきりしています。
若手社会人の方々には、是非お読みいただきたい本です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
興味がございましたら、こちらもお読みください。
ここ1年ほど、マスコミで盛んに使われている言葉に「Z世代」があります。「ゆとり世代」「さとり世代」に続く、今の若者の特徴を表す言葉というべきでしょうか。それにしても、よくまあ色々と新しい言葉を[…]
昨今は、本や雑誌が売れない「出版不況」が続いています。・ 雑誌の休刊、廃刊が相次いでいる・ 大手の書店グループが、店舗を次々と閉店・ 古本屋もどんどん閉店しているといった、本好きの人間には憂うべき事態になって[…]
我が家では、新聞を取っていません。たまに勧誘が来ても、即座に断っています。新聞がなくて困ったことは、一度もありません。現代のネット社会では、必要な情報は新聞以外からも得られるからです。しかし、嫁や私の実家では[…]