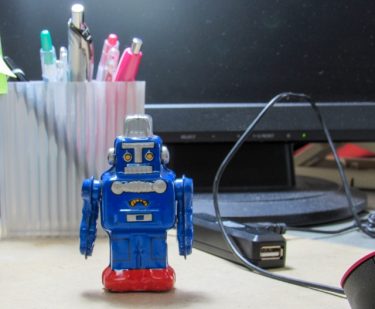21世紀、すなわち2001年(平成13年)以降に生まれた若者世代は、物心ついた頃には既に携帯電話・スマートフォンやテレビゲームが身近にあり、インターネット上でのコミュニケーションが当たり前となっています。
そうした若者たちに「メンコ」や「ベーゴマ」の話をしても、全く話が通じないかもしれません。
仮に知っていても、テレビや本、ネット上での
「昔の懐かしい遊び」
「レトロなおもちゃ」
の情報として認識されているだけという可能性もあります。
メンコで勝つと、相手のメンコが戦利品になる!
この記事をお読みでご存知ない方のために説明しますと、まず「メンコ」とは
トランプのカードくらいの大きさの厚紙
です。
表面には絵が書かれていたり、写真が印刷されています(裏面にもあるメンコも)。
絵柄は古いものだと飛行機・戦闘機や軍艦などのイラスト、新しいものだと特撮ヒーローやアニメのイラスト・写真が主でした。
ただ、この「メンコ」は現代のトレーディングカードとは異なります。
子供たち(基本的に男子)が自分のメンコを地面に並べます。
そして各人が、自分が持つ別のメンコを地面、それもメンコがずらりと並べられている辺りに叩きつけます。
上手く叩きつけると、その際に起こる風圧で地面のメンコがひっくり返り、裏側を向きます。
すると、そのメンコは叩きつけた子供のものになります。
ひっくり返したメンコの枚数が多いほど、戦利品の数が増えるシステムです。
年代や地域によってルールも少しずつ異なり、最後にメンコが元の持ち主に返され、その日の勝者は他の子供たちから駄菓子をおごってもらうなどのルールもありました。
関西地方では、「ベッタン」と呼ばれていました。
ベーゴマは、お互いのコマを弾き合う遊び!
続いて「ベーゴマ」ですが、名前の通りコマ(独楽)の一種です。
一般に知られているコマよりはかなり小さく、鉄製です。
また、中心には芯棒も通っていません。
ベーゴマの底面は一般のコマよりも緩やかなすり鉢状になっていて、そこに細い紐を巻き付けます。
後は一般のコマのように、地面に落とすように投げながら紐を引っ張ると、ベーゴマが地面や台の上でクルクル回ります。
二人以上の複数で遊ぶ場合、お互いのベーゴマがぶつかり合うようにします。
自分のベーゴマの回転が先に止まってしまったり、台の上から弾き落とされると、負けということになります。
1970~1980年台初期までは、レトロでベタな遊びが普通に行われていた!
現代のデジタル世代の若者からすれば、何とも原始的でレトロな遊びとしか思えないでしょう。
私は1970年代半ば~末頃に、実際にメンコやベーゴマで遊んだ体験があります。
しかし、4歳年下の弟が幼稚園~小学校低学年の頃には、ほとんど絶滅しかけていました。
弟が小学校に入学する頃には、任天堂から「ゲームウォッチ」が発売され、小学校3~4年生の頃には同じく任天堂から「ファミリーコンピュータ」が発売されました。
子供たちの遊びが「デジタル化」し始めた第一歩と言えます。
私が小学5~6年生までは、友達同士の遊びでも野球やドッジボールなどの「ベタ」な遊びや、果物の缶詰の空き缶に穴を開け、そこに太めの紐を通してちょっとした「高下駄」を作って歩き回ったりという、
「ザ・昭和」
的なことが普通に行われていました。
私の世代は中学2~3年生くらいで「ファミコン」を知ったので、後の世代の人たちのようにどっぷりとゲーム漬けになる人はあまり見当たりませんでした。
私が大人になってからも、各おもちゃメーカー・ソフトメーカーから様々なゲーム機器、ゲームソフトが発売されました。
しかし、現在40台半ば~50台半ばくらいの人たちは、下の世代に比べるとテレビゲームへの熱中度や関心が平均的にかなり低いのではないでしょうか。
そして、メンコやベーゴマで遊んだ最後の世代だったのではないかと思います。
一時期『ベイブレード』というオシャレな玩具が流行したが・・・。
21世紀に入ってすぐだったか、一時期
「ベイブレード」
という玩具が流行し、子供向けテレビ番組でも大々的に取り上げられた記憶があります。
昔のような鉄製ではなく、プラスチックで格好良い形のコマ(ブレードと呼ぶ?)を発射器に入れます。
そして引き金を引くと、コマが回転しながら飛び出し、ゲーム台の上で相手のコマとぶつかり合うという形式だったはずです。
ベーゴマの進化版のような玩具です。
しかし、「昔の子供たち」からすれば、
「それは違うんだよ~!」
とイチャモンを付けたくなります。
原始的な遊びの中には、あれこれ考え工夫する余地があった!
メンコやベーゴマは、超原始的だからこそ楽しいのです。
そして、子供たちが色々考えて工夫する余地も残されているのです。
メンコだと、持ち方や投げ方を工夫し、地面にメンコを叩きつける時の風圧が強くなるようにしました。
また、メンコの表面にニスを塗り付けて重さを少し増し、めくれにくいようにするという、
ドーピングまがいの加工なども子供たちの間で行われていました。
ベーゴマにしても、買った時点のままではなく、ヤスリなどで削って軽くして回転速度を上げようとしたりと、子供なりに知恵を絞ってあれこれアイデアを捻り出していました。
最後に・・・。
今の玩具も良く出来ていて楽しいとは思います。
しかし、まとまり過ぎていて、子供たちの工夫を促す余地がないように感じます。
男女を問わず、子供という生き物は遊びの中で創造性や柔軟性、社交性を身につけていくのだと思います。
40年近く前に子供だった人間の一人としては、令和の世にもメンコやベーゴマ、ビー玉やお手玉のような原始的な遊びが、新しく出て来て欲しいと願うばかりです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
興味がございましたら、こちらもお読みください。
「超合金」という言葉を聞いて何らかの反応を示す人は、昭和40年代末期~昭和50年代初期頃に幼稚園~小学校低学年だった男性と決め打ちしても間違いないでしょう。平成生まれの人たちにとっては、「超合金って何?飛行機とかの新しい素材[…]