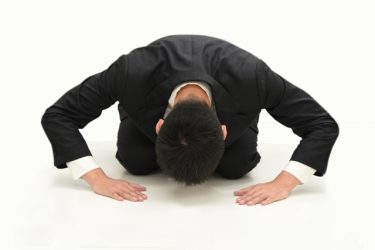このブログでは、
「不動産競売」
「不動産仮差押」
に関する記事を多数書いています。
私は以前、長年にわたり債権回収、すなわち
「借金取り」
の業務に従事していました。
その頃に得た知識や経験が、ネタになっています。
債務者の不動産を担保に取っていなくても、仮差押は可能!
不動産を担保に取っている
「有担保債権」
については、債務者などの返済が滞り回収が困難な場合は、裁判所に競売申立を行います。
担保を取っていない
「無担保債権」
でも、債務者や連帯保証人などが不動産を所有している場合には、不動産仮差押を申立することが可能です。
競売と異なり、すぐに売却ということではありません。
ただ、仮差押がなされた旨が法務局で登記されます。
不動産謄本の登記事項証明書では、甲区欄に表示されます。
そのため、自由に売却することが困難になります。
不動産仮差押には『供託金』が必要!
不動産仮差押の大きな特徴は、申立が認められた後に
「供託金」
を納付する必要がある点です。
不動産仮差押は、不動産所有者の同意なしに申立できます。
そのため、無関係の第三者の所有不動産を、誤って仮差押してしまう事例が稀にあります。
仮差押の解除登記がなされても、仮差押登記の表示そのものは消えません。
「謄本に傷が付いた」
という表現がよく使われますが、大問題に発展します。
そうした事態が生じた際のいわば
「損害賠償」
のために、供託金を納付しておくのです。
裁判所での『審尋』で、供託金の金額が決定される!
供託金の額は、裁判所から一方的に通知されるわけではありません。
申立が受理された後、裁判所から連絡があります。
日時を打ち合わせた上で、申立を行った債権者が裁判所へ出向き、裁判官と面談します。
そこで、裁判官から供託金額を提示されます。
この面談を
「審尋」
と呼びます。
裁判官との面談と聞くと、
「厳しい口調で、色々細かいことを質問されるんじゃないか?」
といった、まるで取り調べのようなイメージを持たれるかもしれません。
ところが、実際は全く違います。
審尋の時間は15分ほど。供託金額も予想できる!
私は一時期、裁判所提出・申立用の文書作成や裁判所・弁護士との折衝を行う部署に在籍していました。
不動産仮差押の審尋に出向いた経験が、10回ほどあります。
裁判官と一対一で行い、こちらは仮差押申立に至った事情を説明します。
裁判官は当然申立書類を確認済みなので、さほど細かい事は聞いてきません。
供託金の額については特に規定もないようで、裁判官が提示する額は大体
「申立債権額の20%」
が一般的です。
裁判官は威圧的な感じが全くなく、事務的な感じです。
こちらも何となくリラックスした気分になります。
審尋の所要時間は、10分~15分程度です。
供託金は『支払保証』がほとんど。審尋当日に手続可能!
供託金は現金で払うことも可能ですが、大抵の申立人は
「支払保証」
の形を取るはずです。
あらかじめ金融機関と、包括的な保証委託契約を締結しておきます。
そして仮差押審尋の度に、
「支払保証委託契約書」(定型文書になっており、支店で手続してもらえます)
を金融機関に持参して印鑑をもらいます。
それを裁判所に提出すれば、供託と同様の効力が発生します。
私はいつも審尋が終わるとすぐに、勤務先と支払保証の契約を結んでいた金融機関の、最寄り支店に向かいました。
そして、支払保証の事務手続をしてもらっていました。
それが済むとまた裁判所へ引き返し、支払保証委託契約書(裁判所提出用)を提出しました。
20分~30分ほど待っていると、仮差押正本を受領できました。
もう随分前のことなので、現在は裁判所でそう迅速に手続をしてもらえるか不明ですが・・・。
最後に・・・。
不動産仮差押を申立する側や、単なる事務の一つとして手続を行う裁判所では、今まで書いてきたような
「まったりした」
あるいは
「ユルい」
ムードです。
しかし、所有不動産を仮差押された側、つまり債務者や連帯保証人などにとっては
「一大事」
です。
結構高い確率で連絡があり、返済の相談にやって来ます。
皆様には、決してそうした事態に陥らないよう、ご注意いただきたいと思います・・・。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
このブログでは、「不動産競売」「不動産仮差押」などの記事を時々書いています。私が債権回収、すなわち「借金取り」の業務に携わっていた頃の経験に基づいています。 [adcode][…]